私がブドウを植えたのは2016年のことでした。
それまで都会で働いていた私は心身ともに疲れて実家に戻りました。次の仕事も見つかっておらず、無職でした。そんな時に父から農作業を手伝って欲しいと頼まれました。実家は米農家で小さい頃はよく田んぼで遊んだり、お手伝いという名の邪魔をしに行っていましたが、大人になってからはほとんど行っていませんでした。
嫌々ながらも手伝いをすると、農作業は充実感で溢れました。太陽の下で体を動かすのはなんとも楽しく、周りに広がる田園風景に癒されました。
そんな時にふと「私が継がなければこの風景もなくなってしまうのか・・」という思いが湧いてきました。その当時はTPPや米価がガクッと下がった年で農業を継ぐのは厳しいと思われるタイミングでした。
しかし、農業を絶やしたくないという思いが日に日に強くなり、農業をやろうと決意しました。

米では継がせられない
農業をやると決意し、父に「米を継ぎたい」と相談しました。そうしたら「これからの時代、米だけでは食べていけないから新しいことをやれ」と言われました。最初は驚きましたが、納得しました。お米は沢山効率よく作らないと利益がでません。私の地元は中山間地域で山が多く、小さい田んぼばかりです。沢山作るには不向きです。
ではどんな農業をする?
農家になるということは起業することに似ていると思います。だからこそどんな分野でやっていくのか相当悩みました。作りやすい作物、利益率の高い野菜、観光果樹園、最新園芸作物など選択肢は沢山あります。最終的には「自分の好きなものをやろう」とブドウに決めました。
ブドウの中でもワイン用ブドウを作ろうと決めました。その理由は「六次産業化の可能性」からです。
私は農業を絶やしたくないという思いから農業を始めました。しかし、私が普通の農家として成功したとしても20,30年後、地元はどうなっているでしょうか。何も変わらないどころか人は減り続け、今よりも疲弊するのは目に見えています。
こんな現状を変えるにはどうしたら良いか調べました。農家一軒だけが栄えるのではなく、もっと周りにも波及するようなやり方はないか・・・
すると新潟や長野、山梨県でワイナリーを中心とした地域活性化の事例が多数見つかったのです。東北にも素晴らしいワイナリーがたくさんありました。
作ったブドウをワインに醸造する。そのワインを地元の食材と合わせてお客様に提供する。地元の飲食店とのコラボ、公共交通機関やホテルとの連携、観光ツーリズムなど先進地のワイナリーは様々な工夫をされてお客様を楽しませていました。
そして、何も無かった土地に何十万人という観光客が訪れて楽しんでいました。また、そのような活動に惹かれて「私もワインを造りたい」という人が増えて、数軒のワイナリーが立ち並んだりしています。そこにまた観光客が訪れる。
その姿にこれからの農業の在り方や畑から始まる本当の農業振興というものを感じました。


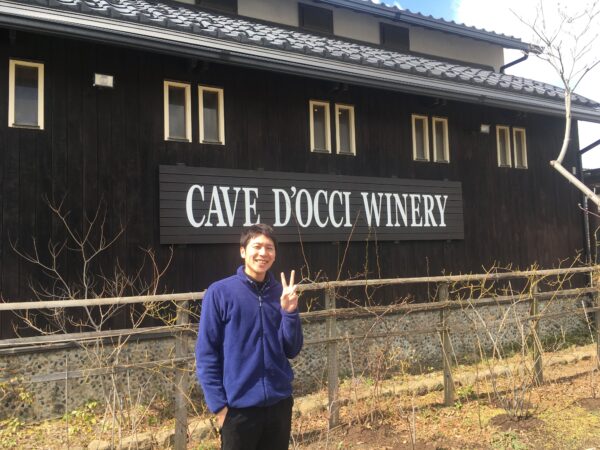
私はワクワクしました。ぜひこのようなことを地元でもやってみたい!こんな大きいのは無理だけどミニバージョンならなんとかなるのではないか?
そんな気持ちで気づいた時にはワイン用ブドウの資材や苗木、指導をしてくる方を探していました。
また、ワイン用ブドウは栽培する土地の味になるということもワイン用ブドウを選んだ大きな理由です。同じブドウ品種でも温暖な地域で栽培するとトロピカルフルーツのような南国系の香りがしますが、冷涼地だと爽やかな柑橘系の香りがします。まさしくその土地を表現する飲み物です。
技術が進化し、砂漠でも果物や野菜を栽培できる時代です。ビルの中で野菜工場というのも一般的になりました。ではなぜ私はこの秋田で農業をするのか?生まれ育った愛着ある「ふるさと」だからです。コンクールで日本一のワインを目指すならもっと栽培条件が良い北海道や長野県で栽培するでしょう。でも私はふるさとを表現するワインが造りたかった。無職となり活力が衰えていた自分を奮い立たせてくれた田園風景。ふるさとを表現したワインを造り販売することで少しでも恩返しがしたかったのです。
そして、2016年にブドウ農家になりました。農家になり初めて分かりましたが農業はとても大変です。さらには6次産業化を進めていくなんてもっと大変です。何をやってるんだろうと打ちひしがれる時もあります。
そんな時、不思議と手を差し伸べてくれる人がいます。「頑張れ!」「美味しかったよ」と声をかけてくれる人がいます。作業を無償で手伝いに来てくれる人がいます。大量にワインやジュースを購入してくれる人がいます。人との縁を繋いでくれる人がいます。「ワイナリー直営レストランはいつからやるの?」なんて私の想像を超えた案を出してくる人までいます(笑)
私一人では上に書いたようなことは不可能でしょう。協力者が不可欠です。このページを最後まで読んでくれたあなたがその一人となってくれたらこれほど嬉しいことはありません。
TOYOSHIMA FARM 豊島昂生

